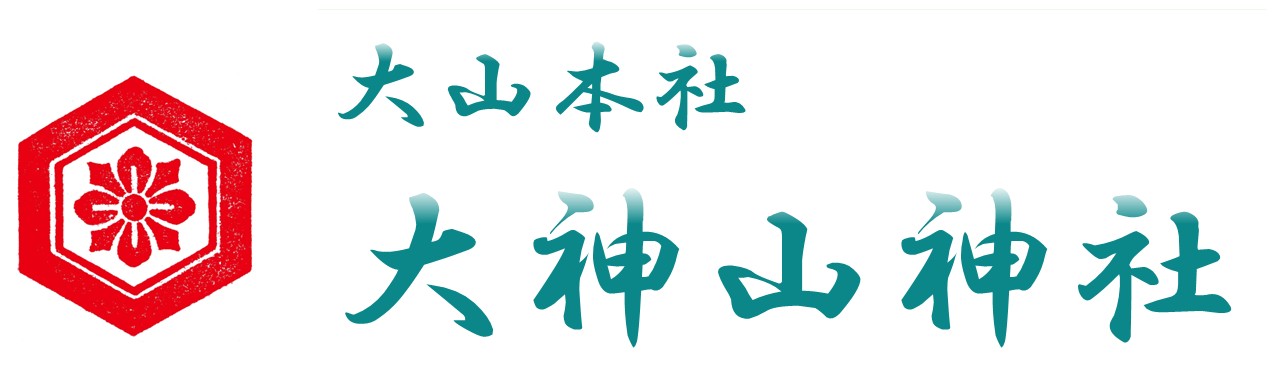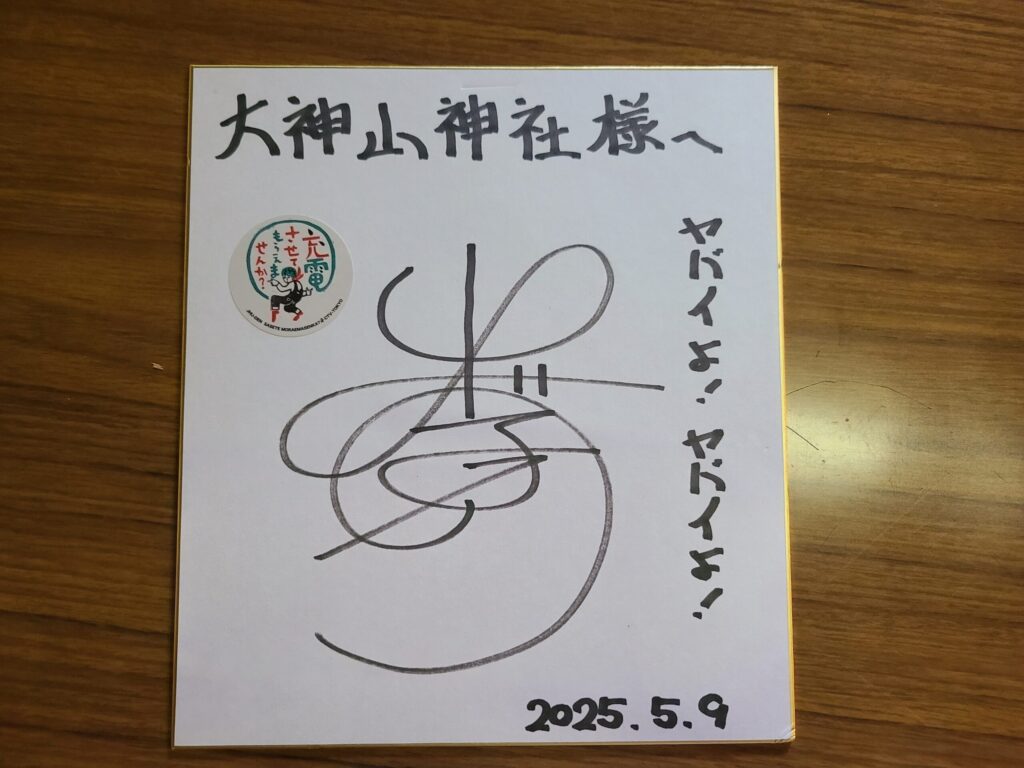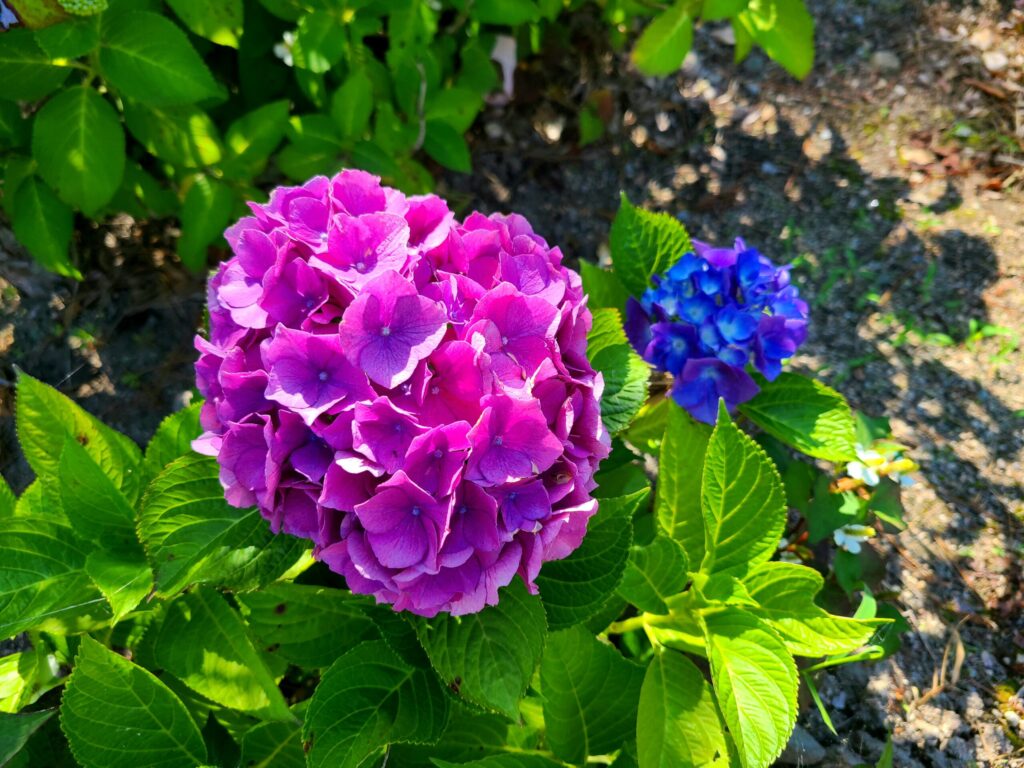大山夏山登山
詳しくは【大山夏山登山】ページをご覧下さい
大神山神社とは

偉大な神のおわす山・『大神岳(おおかみのたけ)』。古代の人々は大山(だいせん)のことをそう呼んで敬いました。その大山信仰の中心が古代より連綿と続く大神山神社です。
今でも大山の御神徳を「だいせんさんのおかげ」と地元の人々は敬意と親しみを込めて崇めています
麓の本社と大山の奥宮の二社をお参りして「大山さんのおかげ」を受けてください
ご祭神
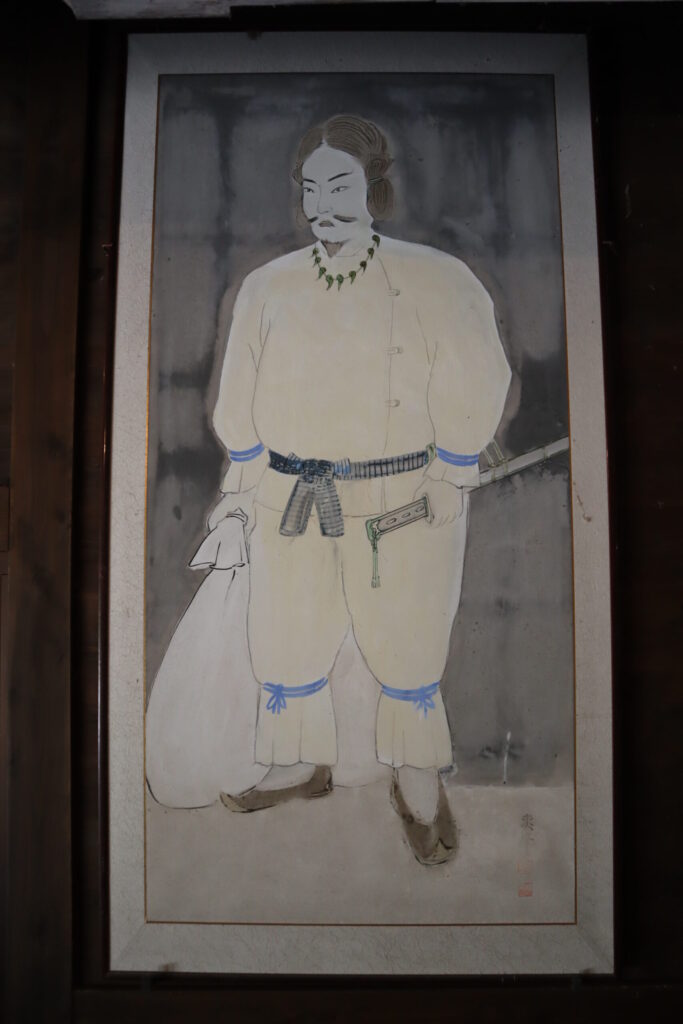
大神山神社の御祭神は大己貴神(おおなむちのかみ)あるいは大穴牟遅神(おおなむぢのかみ・本社)様で、大国主神のお若いときのお名前です。
大己貴神(大国主神)は古事記、日本書紀、出雲風土記等の神話・伝説に多く示すように数々の御神徳をお持ちです。
特に国造りをなされたことから産業発展、五穀豊穣、牛馬畜産、医薬療法、邪気退散の神として有名です
ご神徳
- 農耕 五穀豊穣・農作物の豊作
- 畜産 かつて日本一と称された大山牛馬市
- 病気平癒 因幡の白うさぎ伝説は、日本最初の「医療」に関するエピソード
- 交通安全 ほか、心身および足腰の健康など
- 開運招福 運気を高め、さらなる幸福を
- 勝運 勝負事や試験などの前に
- 良縁 恋愛ほかあらゆるものと縁結びで有名
大神山神社奥宮 令和の御造営
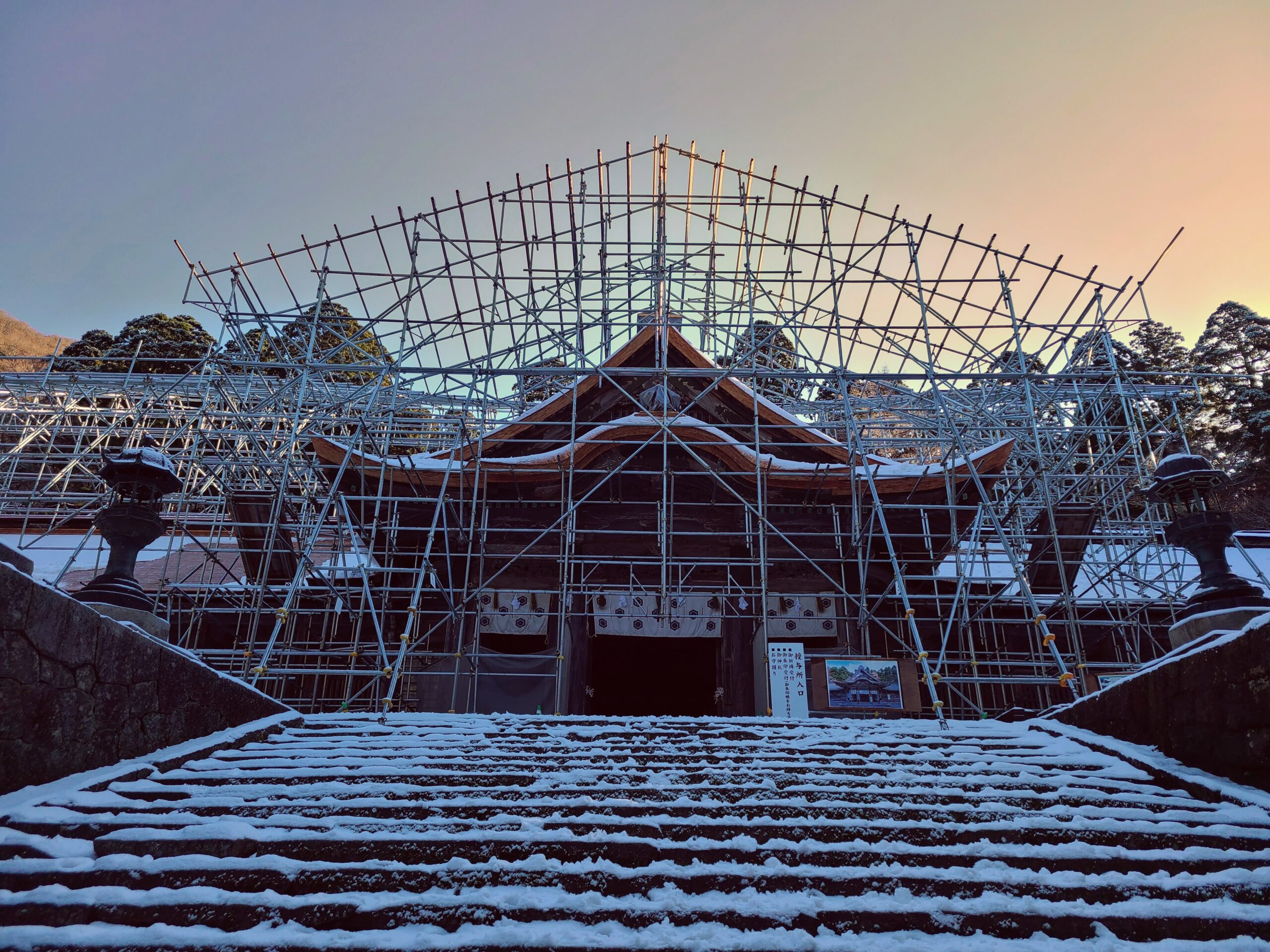
令和御造営
国指定重要文化財
大神山神社奥宮・下山神社
修繕事業
皆様の御奉賛を心よりお願い申し上げます
大山両社詣りのすすめ
奥宮参道の様子
奥宮参道の状況をお知らせ致します
こちらをクリックしてください
神社からお知らせ
- 古式祭について大神山神社奥宮に太古より伝わる神事古式祭(神水汲取神事・もひとり神事)を本年も7月14日・15日の両日で齋行致… 続きを読む: 古式祭について
- 下山神社修繕工事進捗状況現在ご造営中の下山神社社殿 現在古い屋根を全て取り除き、新しい屋根が葺きはじめられたところです とてつもないス… 続きを読む: 下山神社修繕工事進捗状況
- 出川さんが来た先日放送されたテレビ東京 「旅の日」充電旅&バス旅W&バス旅7時間コラボSP旅のスタート地点は、大神山神社奥宮… 続きを読む: 出川さんが来た
交通アクセス
大神山神社本社
〒689-3514
鳥取県米子市尾高1,025
電 話 0859-27-2345
FAX 0859-37-1331
受 付 午前9時から午後4時
~自家用車でお越しの方~
米子自動車道、米子I.Cより車で約5分
米子市街地から山陰道経由で約10分
~電車でお越しの方~
JR米子駅から車で10分
JR伯耆大山駅から車で5分
~バスでお越しの方~
「大山寺」行き「尾高」バス停下車徒歩10分
駐車場 約50台
大型バス ご相談下さい
大神山神社奥宮
〒689-3318
鳥取県西伯郡大山町大山1
電話・FAX 0859-52-2507
受 付 午前9時から午後4時
※天候により前後あり
~自家用車でお越しの方~
米子自動車道 米子I.C
米子自動車道 岸本I.C
米子自動車道 大山P.A(スマートI.C)
より大山方面へ
大山寺旅館街より参道を徒歩約15分
公共駐車場より徒歩20~30分
~電車でお越しの方~
JR米子駅から車で40分
JR伯耆大山駅から車で30分
~バスでお越しの方~
観光道路経由大山寺行き、「大山寺」下車
~駐車場のご案内~
大神山神社奥宮参拝者専用駐車場
大山寺参道途中にあり

ナビゲーション
【鳥取県西伯郡大山町大山16-1】で検索
満車の場合
大山博労座駐車場
【鳥取県西伯郡大山町大山40】
をご利用下さい(冬期間は有料)